昨日、NHKで放映されていた「知的探求フロンティア タモリ・山中伸弥の!?」という番組がとても面白かったです。
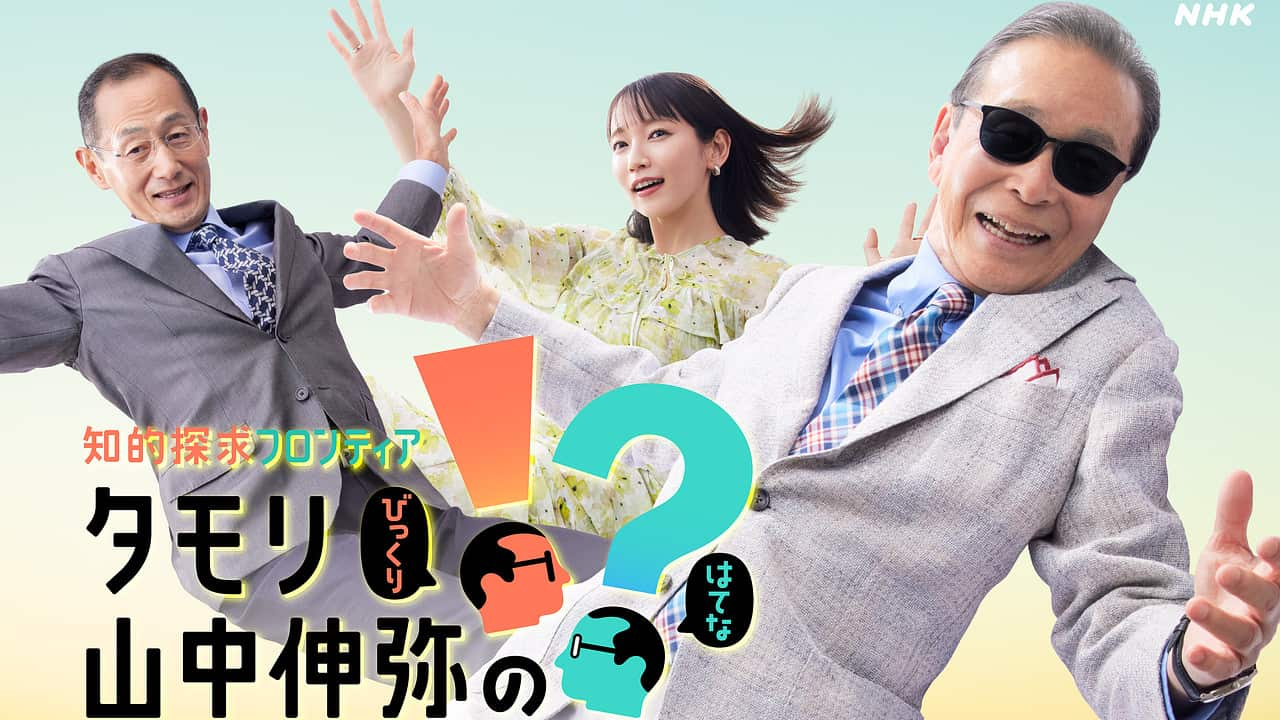
知的探求フロンティア タモリ・山中伸弥の!?
テーマは「AIは人間を超えるか」というもので、まあ言うて巷のネット記事と変わらんやろうと高を括っていたけれど、実際は「人間とはなにか?」という哲学的・根源的に問いに一歩迫るような、非常に素晴らしい内容を分かりやすく伝えていました。
人間や動物は「物事を予測する能力」を生存確率を上げるために経験的・遺伝的に習得してきました。生成AIで用いられているLLM(AIの脳みそ的なもの)は、私らが投げた質問の後に続く言葉を予測して回答を生成するものだけど、実際は人間もLLMと同じように次に繋ぐ言葉を予測して喋ったり、こうして文字を書いています。認知科学や脳科学の領域は、生成AIの領域と密接に繋がっていて、互いに作用しながら「人間とは?」という根源的な問いと向き合い続けています。酔っぱらってるんで話が纏まらないけど、つまりは「ロマンを感じられずにはいられない」のです。
その中で紹介されていた「人間にはできて、AIにはできないこと」として、初めて観測したものを操作すること(例えば、友達の家でお茶を入れるとか)が挙げられていたけれど、ちょうど読んでいた「誰のためのデザイン?」という本にメンタルモデルの話が載っていて、なんとなくそのうちできるようになるんじゃと思いました。メンタルモデルというのは、その物事の理解を容易くする概念を指していて、例えばマグカップを見た時に「何か飲み物を入れるもの」「取っ手に指をかけるもの」のように私らはその形状から経験則的に使い方を一目で理解しています。プロダクトデザインが洗練されるほど、AI(もちろん人間の利用者も)はその情報を容易く汲み取ることができるように思うのです。僕の頭じゃ、いかようにすれば良いのか分からないけれど、何となく「どうあれば良いか?」の抽象的な理念は掴み取れた気がしており、今後は「デザインの在り方」が増々重要になると改めて思いました。
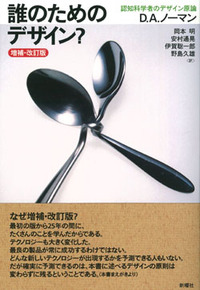
誰のためのデザイン? 増補・改訂版:認知科学者のデザイン原論 - 新曜社
さて。それと同時に、最近思っていることをひとつ。人間はある意味「受肉したボキャブラリー」であり、自分らが発する言葉が自らを定義していると(私は)捉えています。というのは、数年前に100分de名著で放映された「偶然性・アイロニー・連帯」の特集に感銘を受けまして、自分自身の言葉遣いを再定義していくこと(ファイナル・ボキャブラリー)の大切さや、虐殺器官で語られるような言葉の恐怖というものを実感したからです。何が言いたいかというと、私たちはLLMのように会得した言葉を通じて思考を広げ、それを言葉によって伝えてきました。今後は、自分の中にある言葉の多様性を広げていくこと。そして、言葉遣いに気を払うことが増々重要になるのではと考えています。
先日、AWSサミット帰りに元同僚と会話した時、「ヤバい」や「エモい」のような汎用的な言葉を使った表現に慣れてしまうことで、人間の思考が狭まっていくのではという話で盛り上がったのですが、最終的な言葉の多様性は人間ではなくLLMが保持していくのではないかという結論に至りました。SF小説「1984年」に出てくるニュースピークの話で、単語の多様性をそぎ落として思考を狭めていく話がありましたが、まさにあの状態を指しているのではと思います。思考の可能性というのは、論理的に物事を判断しながら想像力を持って理解しようと努めることではないかと(私は)捉えていて、その能力をAIに委ねるか否かという瀬戸際に人間は立たされているのが、今現在な気がしています。人間がどうだの、AIがどうだのという意見は私の中に全く無いけれど、自分自身は「隣人を自分のように愛せる」ような自分でいるために、新しい言葉を会得することや、その言葉を適切に扱う努力を捨てずにもがいていこうと考えています。
酔っ払いの駄文、失礼しました。
では、これにて。